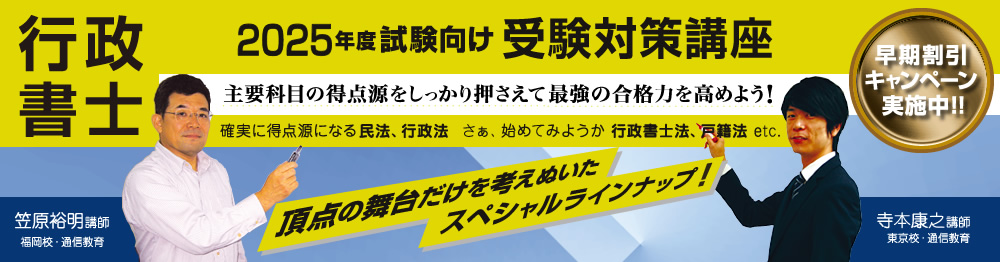�s�����m���������{����܂����I�������ʂ̌����ɁA�܂����N�x�̎肪����Ƃ��Ă����p���������I
�ߘa�U�N�x �s�����m�����u�]
�@���N�`���[�@�����@�o�w�@�u�t�@���{ �N�V
�@�����@�o�w�@�u�t�@�}�� �T��
- [�S�̍u�]]
��N�x�s�����m�����̍��i����10���������߁A�{�N�x�s�����m�����̓���\�z����Ă��܂������A�{�N�x�s�����m�����́A��N�x�s�����m���������Ղ����Ȃ����Ɗ����܂����B
�����Ƃ��A���@�⏤�@�ł́A�����ǂ���A�����肪�o�肳��܂���
���̂悤�ɁA��Ղ�������x�͂����肵����肪�o�肳�ꂽ�{�N�x�s�����m�����ł́A�@�Ղ���������肱�ڂ����ɉ����A���A�A�L�q�����ɓ�����ꂽ�� (�����͂ł��Ȃ��Ƃ��A�e��肩��10�_���x�����_���邱�Ƃ��ł�����) �����i�̉h�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- [��b�@�w]
���P�́A�@�����Ɩ@�̎x�z�Ɋւ�����ł������A�@�������嗤�@�̍l�����A�@�̎x�z���p�Ė@�̍l�����Ƃ�����{�I������m���Ă���A�����ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��ł��܂����B
������x�w�K���ꂽ���ł���A���Ȃ��Ƃ��P��͐����������Ƃ���ł��B
- [���@]
���R�`���U�́A�ō��ٔ����̔����₤���ł����B���R����і��S�̔�����n�ǂ��ꂽ���͏��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA����v�l�̖��Ƃ����܂��B�����Ƃ��A�������́A���Ȃ�ɒ[�Ȏ咣�ł��邽�߁A�����ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������x�w�K���ꂽ���ł���A�S����x�����������Ƃ���ł��B
- [�s���@]
�s���@�́A��N�ʂ�A��{�I������₤��肪�����o�肳��܂����B
�����Ƃ��A�{�����ɂ����ẮA�����댩���ꂽ���ł��A�m�M�������ē����邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ�����A���M�������Ė{�����ɗՂޑԐ��Â��肪�d�v���Ǝv����������܂����B�Ⴆ�A���20�̎��G�́A�������ł͕p�o�̖��ł����A�I�����Łu���v�Ƃ��Ă���̂́A���P�݂̂ł���A�����I������̂��S�O���ꂽ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������x�w�K���ꂽ���ł���A15��͐������邱�Ƃ��ł������ł��̂ŁA���ꂩ��Q�`�R����x�ςݏグ�ė~�����Ƃ���ł��B
- [���@]
���@�́A���30�`���33�������A��{�I������₤��肪�o�肳��܂����B
������x�w�K���ꂽ���ł���A�T��͐������邱�Ƃ��ł������ł��̂ŁA���ꂩ��P����x�ςݏグ�ė~�����Ƃ���ł��B
- [���@�E��Ж@]
���@�E��Ж@�̖��́A������x�w�K���ꂽ���ł��A���ԓI�����邪�䂦�ɁA��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������x�w�K���ꂽ���ł��A�P��`�Q����x���������ɒB���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ǝv���܂����B
- [�����I����]
����x�[�X�̖��ł���A������x�w�K���ꂽ���ł���A�e���U�_���x��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- [�L�q��]
������x�w�K���ꂽ���ł���A���44�ł́u���v�A���45�ł́u�i���Y�����́j�������v�A���46�ł́u�a�̂b�ɑ���i�ړ]�j�o�L�������v�Ƃ����L�[���[�h�́A�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- [��ʒm����]
��ʒm�����ł́A40�����[��������̂ŁA�Œ�U������Ȃ���Ȃ�܂���B�{�N�x�s�����m�����ł́A���͗����̖�肪�ɒ[�ɈՂ����������߁A������x�w�K���ꂽ���ł���A��ʒm�����ɂ�����40�����[���̐S�z������Ȃ��Ǝv���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�
�@