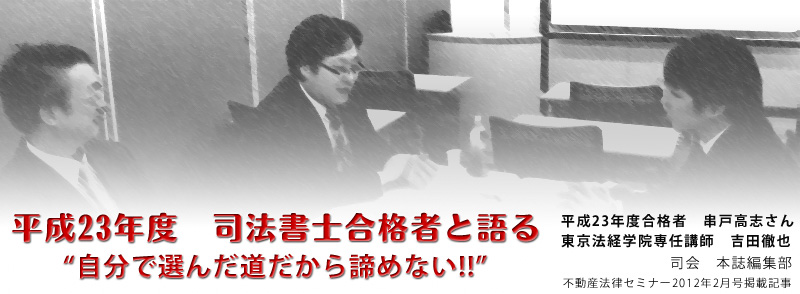
◆独立して仕事をしたい
串戸 明治大学政治経済学部出身の串戸高志と申します。勉強期間は長いことかかってしまったんですけど,諦めないで続けることができたので,それだけは唯一,自分の中では財産になったし,誇れる部分かと思っています。
大学を卒業してみんなが就職する流れがあると思います。私も何も考えずに就職したんですが,自分はサラリーマンって一生続ける仕事じゃないと確信したんです。やはり働いている以上,どうしてもやらされている仕事という意識が抜けきれなかったので,これは自分の人生にとってプラスにならないと思いました。それで,独立して自分でなにか仕事をしたいといろいろ考えました。でも,お金もアイデアもないですし,ある程度社会的にも認められている資格を獲ってやらなければダメなのかと思って,司法書士を目指すことにしました。
吉田 受験回数は何回くらいですか。
串戸 6回です。
吉田 私もそうでしたけれども,サラリーマンをやっていると,サラリーマンが悪いっていうことはないと思うんですが,どうしても自分でなんともしがたい部分が出てきてしまって,「もうちょっとこういうことがしてみたい」ということを考えてしまいますね。実際に私もそうでした。仕事をしていて,このままじゃいけないなんて思って。さあ,これが受かったら,と思って勉強を始めるのです。でも,なかなか難しいですよね。自分が受かろうと思ってもみんながそう思ってやっていますから,なかなか大変です。
串戸 もう廃業しているんですが,父がもともと司法書士だったのです。私が高校生ぐらいのときから多少なりとも興味があったのですが,やはり司法書士は難しいということで自分の中で線を引いていて,そこまで自分で勉強も続けられるかなと思っていました。心の奥底ではずっと考えていたんですけれども,それを封印して就職したのです。でも当時は20代だったので,若いうちに努力しなければ一生後悔すると思って,司法書士の勉強を始めました。
吉田 お父様はかなり長いこと司法書士をやってらっしゃったんですか。
串戸 祖父がもともと不動産業をやっていました。その事業もあったので司法書士は肩書きだけのようだったのですが,たまに案件を受けたりしていたようです。
吉田 私が担当している東京法経学院本科の受講生でも,お父様又はお母様が司法書士をやられている方は結構いらっしゃいます。ただ,どうしても若いうちというのは,自分の両親がやっている仕事はやりたくないとか,ちょっと反発する部分があって(笑),いざ自分がほかの仕事をしてみて,「ああ,やっぱりこの仕事をやってみたい」などという形で目指す方が多いのかなという気がしますね。
お父様は司法書士試験の勉強について何かアドバイスをしてくださったんですか。
串戸 勉強のことについては一切話したことはないですね。ただ,自分が苦労して覚えたことを話すのは楽しいみたいで,ときたま話してくれたことはありますね。
◆楽しいと思える勉強法で継続
串戸 勉強する量が膨大なので,基礎講座に通うたびに「またこんなに詰め込まれるの」という感じで,毎回へこみながらやっていました。まず,講義を受けると,その該当の過去問を解くというのを繰り返すということを初めのうちはやっていました。
吉田 仲間の中には短期合格なさった方もいらしたのですか。
串戸 ええ,いました。
吉田 串戸さんご自身は短期合格できなかったわけですけれども,その原因についてはどう把握されていますか。
串戸 やはり嫌な勉強というのはなかなか続けられないと思うのです。私の勉強法がすこし特殊で,不効率な部分はあったと思うのです。それでもやはり自分が楽しいと思える勉強法じゃないと続けられないと思っていました。不効率かなと思うことはありましたけれども,自分のやり方を貫いていきました。その結果,時間がかかってしまったという感じですね。
吉田 その勉強法というのをもう少し具体的におっしゃってください。
串戸 過去問に忠実というのがこの試験でほとんどの方がやっている勉強の王道だと思います。 けれども,私は最初こそ過去問をやって,平成何年にはこの問題が出たというくらいは把握しているのですけれども,それが頭に入って以降は,いろいろな答練とか模擬試験とかを解きまくるという方法でずっとやってきました。
串戸 最初に基礎講座に取り組んだときは,毎回の授業のボリュームが多いですから,答練にはほとんど手を出せない状態だったのです。そのときは講義が終わったら該当箇所の過去問ばかりやっていました。それが終わって初めて答練に移っていったという感じでした。私の勉強法として,問題を解くことが楽しいのですよ。
吉田 なるほど。
串戸 たとえば知っている知識でもちょっと角度を変えられたりすると,答えられないということが結構あったので,いろんな方面から問題を解けば良いと思っていました。問題にはいろいろな出し方がありますから,インプットよりは,アウトプットを重視するというやり方をずっと私はやってきたのです。
吉田 最初の基礎講座の仲間たちはどのような動きをなさっていたのですか。
串戸 その2年間で受かった人たちはものすごく優秀なんですよ。私と同じことをやっていて,20か月コースを終わって,いきなり最初の答練で全国1位を取るような人たちでした。自分にはそこまでの能力はないと思っていましたので,あまり参考にできなかったです。
吉田 最初の基礎講座のところで,ちんぷんかんぷんだったということはなかったですか。
◆点の知識を線につなげる
吉田 それをどのように克服なさっていったのですか。
串戸 過去問を解いて,一つひとつの知識を身につけて,苦しいながらもそれを続けていくことで「点」の知識が「線」につながっていくように分かってきたと思います。
吉田 不動産登記法に限らず,興味がわかないことを勉強するのは難しいですよね。単に丸暗記しろと言われてもなかなか丸暗記できるものではないですからね。大事なことはどう興味をもってやっていくのかっていうことになりますね。ひとつの方法としては,民法とつなげながらやっていくという方法があります。どこの受験予備校でも民法があって不動産登記法があってという形で分けてやっていますけれど,一番良いのは民法と不動産登記法を一緒に勉強していくことだなと思います。ただ,ある程度の学習の下地があって知識がある方だったら理解できると思うんですが,いきなりそれをやってしまうと,いま何の話をしているのかと分からなくなってしまうので,痛し痒しという気がしなくもないですね。とりあえずやるっていうことしかないですよね(笑)。やっていったら必ず分かるようになりますから。
串戸 そうですね(笑)。
吉田 分かるようになってくると,「じゃあこれはどうなんだろう」,「こっちはどうなんだろう」と,いままでは分からなくて単に暗記していたものが,頭の中でつながっていって,一通り全部終わったときに初めて「これってこういうふうになっていたのか」と思うようになるものです。これは不動産登記法に限らず,すべての科目について言えることですね。民事保全法だとかで,初めて不動産登記法でやったことが活きてきたりします。それまでは分からないことはいっぱいあります。だから,よく言いますけれども,諦めちゃだめなんです。諦めてしまったらその時点で分からなくなってしまいます。いま分からないことがあったとしても,それは必ずそのうち分かってくるようになってくるわけです。ただ,いきなりは分かりませんよ,と言っています。ひと言で「こうすればいいですよ」と言ってあげられればいいんでしょうけれども,なかなか難しいのです。
司会 串戸さんは2年間の基礎講座を終わって,答練に移っていかれたわけですけれども,そのあたりのご自身の判断についてはどう考えていらしたのですか。
串戸 もう一回基礎講座を受けても,あまり自分の中でプラスにならないなと思ったのです。過去問にはどんなものがあるかを,ある程度は把握することができているという自覚がありましたから,あとはちょっと問われ方を変えられたときに対応できることが必要だと思いました。ちょっと勘違いしている方も結構いると思うんですが,私は答練で知識を得ようとはあまり思っていなかったんです。出題の角度を変えられたときに対応できる力を磨くためというのが大きかったですね。もちろん,法改正とか,そういう部分では答練で得る知識は有効だと思います。
吉田 勉強された期間は6年間あるわけですが,基礎講座が終った3年目から6年目までの勉強の仕方で,転換は何かありましたか。
串戸 それはもう自分のやり方を貫いていきました。問題を解きまくるという基本的なスタイルは一切変えなかったですね。仮に平成23年度で受からなくてもそれを変えるつもりはなかったです。
吉田 でも,3年目,4年目,5年目と落ちてくると,やっぱり自分の勉強方法に疑問や不安はなかったですか。
串戸 正直,択一は20か月コースを終わって1年目は足切りに引っかかったんですが,2回目からは基準点を超えるくらいは稼げたので,知識の得る方法とアウトプットの仕方については間違いないという確信がありました。ただ,性格的に不注意な面が多々ありまして,記述式であと1点足りないとか2点足りないとか,そういう感じで落ち続けていました。

問題を解くことが楽しい
◆答練では自分の弱点を把握する
吉田 答練を受けるとひと言で言ってしまいますが,いろいろな意味がありますよね。単に新しい知識を得ようとする場合もあるし,先ほど串戸さんが言ったように自分の持っている知識を確認するために使うという方法もあります。多くの方が,答練で問題を解けば点数が上がっていくだろうという勘違いをされている気がします。いくら新しい知識を身につけたからといって,実際にそれが本試験に出てこなければ点数には反映されないわけです。だから,必要なのは,本試験につながる形での答練の受け方です。それをやっていかないと,単に問題を解いて自分がやったつもりになっていても,いざ本試験を受けると点数が伸びきらないということになってしまいます。ですから答練を解くときにも本試験と同じように解くことが必要です。 答練を解いたとき,自分が分からない問題が出てきたときにどうするかというと,一番大事なことは,答練で分からない論点が,自分の知識の中にあるのか,ないのか判断することです。自分の知識になければ解けなくて当たり前ですから,仕方がないですね。ただし,知識があるのに覚えていなかった,理解していなかった,覚えたつもりになっていたという場合はそこが自分の弱点です。この自分の弱点をどう把握していくのかということが大事です。そのことを勘違いしてしまうと,やっているんだけど実力が伸びきらないということになります。逆に,しっかりそういった形で答練を使っていただくと,自分の弱点をどんどん克服することができますので,実力もさらに伸びてくると思います。串戸さんはすごく特殊な方法でやっているとおっしゃっていましたけれども,決してそんなに特殊ではないと思います。要するに新しい知識をむやみに詰め込むということじゃなかったんですよね。
吉田 自分のやってきた知識というものを確認して。たとえば一つの問題,一つの知識に対して,真正面から見た場合というのは分かっている。では,それを裏から見たときや横から見たときに分かりますか,ということだと思います。それが分からなかったら,やっぱり分かってなかったんだな,じゃあそこをしっかりやろうっていう形で串戸さんは肉づけされていったんでしょうね。
串戸 はい。
吉田 角度を変えた問題が出てきて解けなかったとしますよね。そういうものを元に返ってチェックするとか,テキストに書き込むとか,何か整理するようなことはなさったのですか。
串戸 長年勉強していると,これは出そうだなという嗅覚が働いてくるんです。そういうのはノートにまとめていました。そのほかに過去問や答練に出た判例などは,判例付きの六法にマルを付けて,これは何時の答練で出たとか,平成何年の試験に出たという形で記録して,まとめるようにしていました。
◆民法は判例を理解してから覚える
吉田 それでは,科目別の具体的な勉強の仕方に入っていきたいと思います。まず民法はどうのように取り組まれましたか。
串戸 民法は一番この試験の中では単純な暗記が少ない科目だと思います。結果的には判例を覚えるんですが,なぜその結論に至ったかということをまず自分で考えてみました。最初のうちはなかなか趣旨が分からなかったので,分からないことはなかなか覚えられませんでした。そのため,最初は民法が一番得点も伸びなかったですね。それでもやはり一つひとつ地道に覚えることの繰り返しでやっていったら,今年の試験では最後の二択で迷ったときに正解を選べるようになってきたんです。最初のうちはそれを外していたんですけれど。やはり理解が深まってきたから,迷ったときに微妙な判断の選択の精度が上がってきたのだと思います。そうなるためには一つひとつ地道に理解してから覚えていく,それしかないんではないかと思います。

弱点を把握することが大事
◆憲法は答練で問題数をこなす
串戸 この科目が一番対策にも悩むし,勉強もしづらくて,おもしろくもなかったのです。過去問も少ないですし,そこから考えると,やっぱり答練で問題を解いて,そうすると次はこれが出そうだなとか,推論である程度は読めてくるのですね。確認はしていませんが,おそらく司法試験で昔使われた問題を変形するとかして出題されているのかな,と個人的に考えています。そのせいか,論点は限られていると思うのです。そういう面で憲法に関しては,過去問だけでは足りないので,答練で問題数をこなすことが大事なのではないかと思います。
◆会社法と商業登記法はワンセットで
吉田 会社法が分かっていないと商業登記法はまず解けないですね。だから商業登記法と会社法をまとめてやるのは効率的ですね。実際に私の本科でも会社法と商業登記法をセットでやっています。会社法で実体上の流れをおさえていって,それを商業登記でどう登記するのか,なんてやっていますね。とくに会社法に初めて取り組む方というのは,実際に自分が手に触ったこともないし,見ることもできないことをやっているわけです。これが,民法だったらある程度一般常識的な話が出てきます。A さんとBさんが争いましたという形で。どうなりますか。
◆不動産登記法は書式から入るとよい
吉田 不動産登記法の択一は,記述式とは切っても切れないものです。択一向けの勉強だけをして択一が解けるようになるのかというと,難しいと思います。学習の方法としては,まず記述式の書式をやっていって,ある程度書式というものはこういうものなんだなということをおさえた上で,不動産登記法の総論的な択一の話に入っていくと,学習しやすいと思います。いきなりテキストを読んでみて択一の問題を解けと言われても難しいですよね。やったこともなければ見たこともないことを理解しろというのは会社法と同じようにかなり難しいです。それを書式という具体的な形にしていって,こういった書面が必要なんだ,それなら通則的に考えたら結果的にこうなっていく,という形で学習していくとスムーズに進むと思います。
串戸 いちばん最初は最低限の知識を入れないとそういう方法も採れないですが,不動産登記法に出合ってから2か月,3か月くらい経ったときには,ほんとうに簡単な2連件くらいの書式のベーシックな部分は意識しながらやっていきました。実際に最初そういうベーシックな書式を並行して勉強していかないと,理解が進まない部分はあると思います。

問題を解くことが楽しい
◆8問中7問取りたい商業登記法
◆民事訴訟法はイメージをつかむ
司会 民事訴訟法関連を苦手とする方は結構多いのではないでしょうか。
吉田 確かに多いですね。民事訴訟法は面白くないといえば面白くないですからね。自分がやったことがないことをやるわけですから。まだ会社法のほうが何となくイメージがつきますから楽しいですよね。ただ,問題数としてよくマイナー科目なんてひとくくりに言われてしまいますけれども,民事訴訟法で5問,執行法で1問,保全法で1問,合わせて7問ですからね。決してマイナーなんていう失礼な言い方はできないはずなんです。だから,ある程度力を入れていかなければいけないのです。先ほどおっしゃっていたように,民事訴訟法に関してはちょっと過去問とは傾向が変わってきているというか,単に過去問をやっていたからといって点数が取れるかといえば,難しいレベルになってきています。ただ,それは基本的にほかの人も同じですから,判例ばかりおさえていくというのも逆に時間とその効率を考えてしまうとどうなのかなという気がします。どうしても理解しづらいとか興味がわかないという方は,逐条解説である『コンメンタール』を読んでいただくと,「ああ,なるほどな」という部分があると思います。
資格予備校はどこも同じだと思いますけれども,マイナー科目みたいなくくりで行われているので,それほど時間数を使えないのです。たとえば民法と同じくらい時間数を使えるかといえば,実は使っていないはずなんです。それで,どうしても表面的な話になってしまうし,もっと突っ込んだ話をしたくても時間が足りないということになってしまいがちですね。どうしてもイメージがわかないというときには『コンメンタール』を読んでいただくとイメージがつくのかなと思います。ただし,あまりにも細かいところまでやってしまうと,逆に本試験で出ないことまでやってしまいますので,効率が悪くなってしまいます。答練をやりながら答練の解説で理解できればいいですし,理解できな かった場合には『コンメンタール』を使って読んでみて,なるほどこういった判例はこういった意味があるのかという形で学習していただくことがいいと思います。

民訴法はコンメンタールでイメージ化を
◆記述式は隠れている論点を探す
串戸 記述式については,どうして足切り点さえ突破できなかったのかと,今でも分からない部分があります。やはり私の不注意な性格が影響していたと思います。注意文を読み落として,たとえば添付書面の書き方を指定どおりに書かなくて,それで自己採点と照らし合わせてみて5点くらい引かれていることがありました。あとは,時間がなくてテンパっているということもあるんですが,委任状を自分の勝手な判断で 必要ないと思い込んで書かなかったこともありました。それについても各0.5点だとしても,5欄あればマイナス2.5点ですから,ほんとうに2点,1点の差で自分は落ち続けてきました。最後の詰めの甘さが出たのではないかなと思っています。
私がそういうミスを重ねたのは実は不動産登記法なんです。商業登記法に関しては,それほど本試験では苦労した覚えはありません。ただ,23年度は時間がなくて最後までたどり着けなかったんですけれど。どういう勉強法がいいのかということについて確信を持って言えることは,今になっても正直ないですね。記述式に関しては,択一に比べたら対策を取りづらい科目です。
司会 よく受験生は1日に1問ずつ解くというようなことを言いますが,具体的にはどうなさっていたんですか。
串戸 苦手なものですから,どうしても後回しになっていました。理想は1日に1問やれば良いと思うので,自分にノルマを課していたんですけれども,そこまでできなかったというのが実際のところです。でもやはり1問ずつやるのが理想的な勉強法ではないのかなと思いますね。択一を突破しないと採点されないので,どうしても択一ばかりに気持ちがいってしまいがちです。ある程度択一ができるようになれば,一日 の勉強の最初に記述式を持ってくるようにすればノルマをこなせると思います。私は,どうしても択一をやりたくなるのですけれども,23年度試験対策では択一と一緒に記述式もやるようにして,記述式問題をこなす回数を増やしました。
◆誰かに強制されて始めたわけではない
串戸 基礎講座が終わったあとで,自分なりに過去問もやって初めて答練を受けたときに25点くらいでした。思ったよりも全然取れなかったので,そのときは自分の能力が足りないのかなと思って本気で後悔しました。ただ,もう引くに引けない状況もあったので,もう倒れるときには前のめりにという感じで,とにかく「進め,進め」と思って,自分の思うやり方で突っ走ってきました。
吉田 あとに引けない状況というのを少し具体的に説明していただけますか。
串戸 自分でこれをやろうと思ったので,誰かに強制されて始めたものでもありません。もし,ここで諦めることになったら,たぶん自分は一生そういうことを背負っていくことになるんじゃないか,という恐怖感がありました。結果を出すまでは絶対に諦めないという意識を持っていました。
吉田 そのモチベーションを維持していく自分なりの方法はあったのですか。
串戸 先に独立している友人や不動産業界で働いている友人,金融業界で働いている友人もいますので,そういう人たちと酒でも飲みながら,「じゃあいつ仕事くれるの」みたいな(笑),皮算用なんですけれども,そういうのが楽しくて,辛くなると友人と会って酒を飲みながら夢を見るというのが,ストレス解消になりました。
吉田 モチベーションを維持するのは大変に難しいですよね。どんなに短い受験期間だったとしても,1年半はありますからね。それでは,1年半全力で突っ走れるかといったら,実際は難しいですよ。たかが1年半ではありますけれども,全力で突っ走ることはできませんね。それに,1年半あったら司法書士の知識が楽に身についてくるのかというと,そういうものでもないですからね。1年半というのは,正直言って短いです。実はそこが難しいところなのです。全力で頑張ると1年半は長いですけれども,知識を得る時間としては短いという矛盾があります。そんな中で,勉強してもなかなか点数が伸びないと,自分ではこんなに頑張っているのに,なぜできないのだろうというところで,モチベーションが下がってきて,もうだめだなんていう方を見たことがあります。勉強を始めたからといって,すぐに点数が上がっていくかというと,そんなことはないんですよ。ある程度勉強をしている期間が続いてから,やっと少しずつレベルが上がっていくものなんです。いきなりガツンと上がることは滅多にないです。実力は少しずつ上がってくるということです。
司会 合格した後の自分を振り返って,ここのところで,合格に結び付いたんだといういうような出来事はありましたか。
串戸 私は答練を解きまくるという勉強方法をとりました。それは過去問ではどれくらいまで聞かれているかということを自分なりに把握しているつもりでいたので,この方法ができたのです。過去問の問いかけの深さについても,何年後にはこのくらいまでくるのかなというのは何となく嗅覚が働いてきていました。答練で出題された論点であっても,これは絶対出ないよという問題を取捨選択する必要があります。それを判断できた上で,答練を重ねて解いていくという方法を私はとれたと思います。いま振り返っても,ほかにもっと効率的なやり方があったかもしれないですけれども,やっぱり自分が続けられる方法でないと継続できないですから,時間はかかりましたけれども,自分なりの方法を貫いたからこそ,結果を出すことができたのだと思います。
◆短期で合格することが得なのか?
串戸 最初の受験とその次の年の受験では,試験が終わっても年内は2,3時間の勉強時間でした。それで直前期になると仕事を休ませてもらって,7,8時間やっていました。3年目,4年目以降は,年内は1時間,2時間で,最低限の知識を忘れない程度にテキストなどをパラパラ見るくらいでした。毎日は勉強しないですし。そういう感じでやって,直前期になって同じように8時間くらい時間をとってやるという感じでした。
司会 直前期というのは3か月くらいですか。
串戸 最初のうちは,たとえば3年目であれば4月くらいから始めたりしていましたけれども,23年度は4月の終わりくらいからでした。どんどん知識が定着してくれば,一度覚えた知識で,ある程度覚えていれば,それをもう一度呼び起こすというのはそれほど苦労ではないのです。最初の頃は量が多いという意識がすごく強かったのですけれど,知識が定着してきて択一の点が伸びるにしたがって,「思っていたほど多くないじゃん」という意識が出てきました。そうすると余裕もでてきて,これだけやればこれだけできるなというのが読めてきました。
◆仕事をしながら勉強するには
串戸 受験専業の人でも1日12時間も勉強するというのは,人間ですからできないと思います。であれば,毎日残業で10時,11時ではどうしようもないでしょうけれど,そうじゃないのであれば,隙間時間をうまく使うという形で,この試験やっぱり量は多いので,何回も何回も愚直だけど繰り返す,それしかないのです。本当にそういう隙間時間を使って繰り返すしか方法はないのではないかと思います。
司会 なるほど。では7,8時間やる時期というのは,あらかじめ勤め先におっしゃっていたわけですか。「わたしは受験生ですからその時期は仕事を減らしてください」みたいなことを。
串戸 もともとの食品会社の営業マン時代は,ほんとうに毎日夜の10時や11時レベルだったので,さすがにそれではいくらなんでも受験勉強はできないと思い会社を辞めました。その事情を話して派遣社員になりました。毎回,仕事で行く現場が変わるので,早いときには朝4時に家を出て夜の8時に帰ってくるとか,ちょっと読めない部分がありました。ただし,早いときは午前中に帰ってこられることもあったので,そういうときに時間を有効に使いました。忙しいときには移動中にミスノートを眺めることくらいしかできませんでしたが,試験前は休みを取らせてもらえました。その点では恵まれていました。
司会 吉田先生,いま働きながらの受験生はかなりいらっしゃると思いますが,アドバイスをお願いします。
吉田 そうですね。実際に私がここ最近見ている中でも,完全に仕事を辞めて受験専業でやっている方はほとんどいなくなりました。私が受験勉強した頃というのは,逆に働きながらやっている人は少なかったと思います。ほとんどの方が専業でやっていたと思います。でも,これだけ不景気になってしまうと,とくにいま正社員についている方には,社員を辞めてとまではちょっと難しいのかなと思います。ただ,それは人それぞれですからね。学生さんもいれば社会人もいれば,もっと年上の方もいらっしゃる中で,みんなそれぞれの環境の中でやっていて,たとえば学生で,時間が自由になるからといって,必ずしも有利というわけではないですからね。また,働きながらで,時間がないから不利というわけではないのです。
司会 ありがとうございました。口述対策について,主に司法書士法を含めてお願いいたします。
串戸 私は東京法経学院の口述模擬面接を受けさせていただいて,そこでいただいた冊子を覚えるという,それぐらいですね。逆にそれ以上やってもあまり意味がないと思います。
吉田 口述に関してはおっしゃったとおり,特に勉強する必要はないですよね。いままでちゃんとやってきて,筆記試験が受かっているんだったら,当然分かって然るべきですから。とは言いながらも,結構時間が空きますからなかなか難しい部分もあるんですけれども。ただ,悪かったからといって,答えられなかったからといって落ちるという類のものではありませんので。しっかりと受け答えができればいいと思いますね。
◆東京法経学院の求人情報で
串戸 司法書士事務所に入って,勉強と実務の違いが結構自分の中でギャップが大きくて,一杯一杯な状態なのです。独立するにしても,受けた依頼をしっかり処理できなければ独立も夢のまた夢なので,まず簡単な案件でもしっかりキッチリと処理できる最低限の力を付けていって,そこから初めて,どうやって攻めていってお客さんを取ってくるかということまでいけると思いますので,まず一つひとつの案件をミスなくそつなくこなせるようにいまは一生懸命覚えている最中です。
司会 具体的にどうやって司法書士事務所を探されたんですか。
串戸 いま勤めているところは,東京法経学院の求人募集からです(笑)。
司会 ああ,そうですか。当学院が役に立って良かったです(笑)。
串戸 結構条件がいいものが,東京司法書士会にもあるんですけれど,東京法経学院に載っているもののほうが条件がいいのです。
司会 担当者が喜ぶと思います(笑)。それはお役に立って何よりです。それで独立のことまで事前に話をして,事務所に入られたのですか。
司会 なるほど。じゃあ所長も了解の下ということですね。
串戸 そうです。
司会 まだ試験に受かっていない受験生の読者の方たちに,将来の希望を含めて吉田先生からアドバイスをお願いいたします。
吉田 司法書士の試験は非常に難しいものではありますが,受かってお終いというものでもありません。合格はスタートです。自分の夢をこれからどうやって実現させていくのか。その形は人それぞれだと思います。不動産登記をやりたい人もいれば商業登記をやりたい人もいる。また経営コンサルタントみたいな形で会社に関わっていきたい人もいます。いろいろなやり方があっていいと思います。司法書士会の研修に行くといろんな話が聞けます。特に新人研修などではいろんなところに特化して,「あ,こんなことやってるんだ」というように,おそらく受験勉強をやっているときにはそんなこと思いもつかなかったようなことをやっている方がいっぱいいらっしゃるわけですね。だから自分の興味がどういったところに湧いていくのかということを楽しみにしながら,勉強をしていただきたいですね。司法書士の方が書いた自分はこ ういうことをやっているというような本も出ています。たとえば成年後見だとか,会社関係をやっている人もいっぱいいますし。自分が何をやりたいのかという夢や希望を考えながらやっていくとモチベーションも上がると思いますね。単に勉強して受からなきゃいけないんだと思ったらつまらないですからね。受かって,じゃあ何がやりたいんだって考えながらやったほうが絶対楽しいですからね。